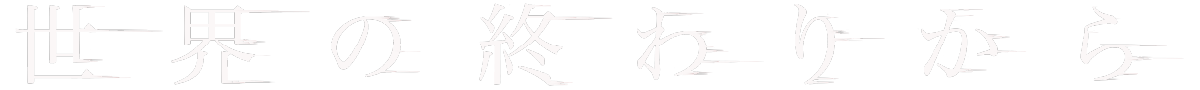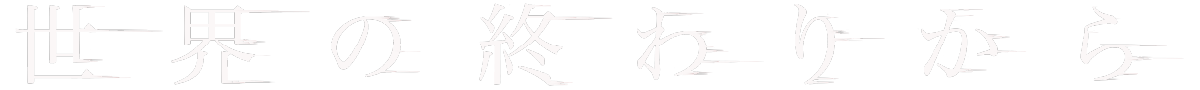SPECIAL
【原罪論の現代的水脈】
宮台 真司
紀里谷和明監督『CASSHERN』(04)が、各方面で否定的な評価を受けている。いわく、言葉のメッセージが前面に出過ぎだ。いわく、映画ではなく映像だ。総じて、前回『殺人の追憶』『ミスティック・リバー』について論じた「映画ならではの表現」が皆無だ——云々。
それのどこが悪いのか。ササキバラ・ゴウ「おたくのロマンティシズムと転向」(『新現実』Vol.3)が述べる通り、60年代のTVアニメが、憲法九条リアリティに支えられつつ、「正義」と「平和」を賛える暑苦しいメッセージを噴き上げていたという事実を、忘れたのか。
確かに、暑苦しい言葉の奔流に、随時変化する絵(CG主体の動画)が付けられた「動く紙芝居」だと言える。だが、そもそも日本のアニメの源流に紙芝居があるのだ。紙芝居が既に失われた今日、映画が電脳的紙芝居をやっても少しも構わないではないかと僕は感じる。
京都で過ごした小学校時代、紙芝居屋が売るジャム煎餅を舐めつつ紙芝居を見ていた僕は、懐かしさに落涙した。問題は、ササキバラ説に従えば「九条リアリティの空洞化で本来ならあり得なくなったはず」の暑苦しい言葉の奔流を、今どんなリアリティが支えるかだ。
本作は神話だ。先のリアリティを「イエスはメシアならず」という「神話否定的神話」--「AでなくBでなく…」という否定神学的神話--で開示する。要は「我らが原罪いまだ贖われず」。だがユダヤ教のメシア待望に加担せず、「原罪の贖われる時は永久に来ず」と断言する。
その意味は?。原罪とは、境界設定の背理のことだ。第一の背理は、「我らとはこれ誰ぞ」の謂い。我(われ)が、我のみならず「我ら全て」を救おうとするとき、「我ら」はいつも「我らなるざる者」を軽んじ、踏みつけつつ、しかもそれに気付かず平然とする傾きがある。
ときには「我ら」が生き延びるべく、敢えて「我らならざる者」をこしらえ、たかが人のクセに、あたかも造物主=神のごとく振る舞う。だが、そこまでして、何ゆえ「我ら」のみ生き延びたがるのか--。宮崎駿『風の谷のナウシカ』漫画版七巻を髣髴させる問題設定だ。
イエスがヨハネより受けたバプテスマ(水の洗礼)をイメージさせる液体中で、死んだ東鉄也は、本人の望まざる復活を遂げる。「復活のイエスがキリストとなりしが如く、復活した鉄也はキャシャーンとなりき」。然るに、イエスと違い、キャシャーンに奇跡は起こせない。
キャシャーンこそは、まさに原罪を反復する者の謂いだ。キャシャーンとして復活する前、東鉄也は、戦闘中に仲間を庇護うべく、罪なき女を射殺した。その彼女こそは、後にブライの名を語り、新造人間を率いて、人間どもに敵対することになる男の、最愛の妻であった。
その事実をキャシャーンが知ったとき--ブライがかつての自分と同じ人間だったと分かり、かつ自分が虐殺したのが彼の愛する妻だと知ったとき--、目の前にあり得た境界設定は融解し、キャシャーンは闇に沈まざるを得ない。ことほどさように「我らとは、これ誰ぞ」。
原罪を構成する、境界設定の第二背理。それは「世の摂理は人知を超える」の謂いだ。たかが人のなす区別(知恵)は、神のなす区別(摂理)とは自ずと異ならざるを得ない。だからこそ「究極の善意」が「究極の悪」をもたらし、意図せざる帰結のオンパレードとなり得る。
鉄也の優しき母ミドリは、行き倒れた新造人間たちを救う。生き延びた新造人間は、自らを抹殺したがる人類の手を逃れ、地の涯まで行き着く。やがて彼らは新造人間の国を作り、人類絶滅に乗り出すだろう。助けた相手に殺される——浦沢直樹『Monster』を髣髴させる。
そもそも新造細胞は、鉄也の父が妻ミドリを病から救うべく開発した。然るに、新造細胞から生まれた新造人間たちは、自らを行き倒れから救った妻ミドリを逆に監禁、人類への殲滅戦を挑むだろう。ことほどさように、世の摂理は人知(人による区別)を超えるしかない。
イエスが人間全体の原罪を背負って身に受けたパッション(受難)のお陰で、「我ら」は受難を免れた。と思いきや、「我ら」の原罪はいまだ贖われぬままなのだった。ならば、永遠の受難は必定だろう。なぜならば原罪は、構造的に不可避なるがゆえにこそ「原」罪と呼ばれるからだ。
イエスも結局はメシアたり得ない。今後もメシアは出現しない。むろん神やメシアが消滅しても「我ら」の原罪は消えない。とするなら、「我ら」は原罪を抱えたまま「神なき世界」を生きるしかない。だが、いかにして?これが『CASSHERN』の黙示録。青臭いと笑うなかれ。
人間と非人間。知的存在と非知的存在。友と敵…。およそ人のなす区別は恣意的で、無数の抑圧と自業自得を生む他ない。しかし人は区別をぜずには生きられない(原罪)。とするなら、どうすればいい?そう。「区別を受け入れつつ、永久に信じずに、実践する」しかない。
まさにデリダの「破壊ならぬ脱構築」の定義。あるいはローティの「リベラリズムならぬリベラルアイロニズム」。『パッション』とCASSHERN』を観れば、イエスの喩から現代思想へと連なる原罪論の水脈が見出されよう。我々の可能性と不可能性が、まさにそこにある。